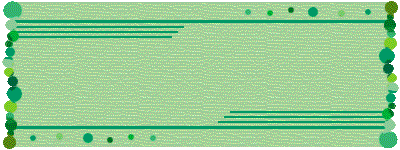
| 11 月 分 添 削 と 寸 評 | ||
| . | ||
| 日時のたつのは早いもので11月も終わり、今年もあと1ヶ月 | ||
| を残すのみとなりました。 | ||
| 12月は師走と言いますが、師走と言えば何かしら気ぜわしく | ||
| 感じるのは子供の頃の記憶が強いからでしょうか。 | ||
| 寒さも一段と厳しくなります。ご自愛の上ご健吟ください。 | ||
| 今月もいい句が沢山ありうれしく思っています。相変わらず | ||
| 私なりの添削と寸評をします。 | ||
| . | ||
| 番号 | 添 削 & 寸 評 | 俳 号 |
| 1 | 捨て案山子時雨の中でふるえてる | 石の花 |
| <添削> ひゅうひゅうと風鳴ってゐる捨案山子 | ||
| 「案山子」は秋の季語、「時雨」は冬の季語です。「ふるえる」といった動詞は | ||
| なるべく使わない方がよい。このように詠んでみました。 | ||
| 「捨て案山子」と名詞の場合は送りがなは不要です。 | ||
| . | ||
| 2 | 大手門句帳片手に菊花展 | 媛 香 |
| <添削> 友といく句帳片手に菊花展 | ||
| 「大手門」と名詞切れになるのはどうかと思い、このように詠んでみました。。 | ||
| . | ||
| 3 | 稲妻の胸を貫く仕舞風呂 | さつき |
| いい句です。さぞびっくりされたことでしょう。 | ||
| . | ||
| 4 | 冬空にコーチの怒声絶え間なく | まこと |
| いい句です。厳しい練習をしてこそ上手くなるのです。冬空ですから | ||
| 私にはラグビーが想像されます。 | ||
| . | ||
| 5 | 冬の山あまたの風車動かざる | 石の花 |
| 私には句意が今一つ分かりません。悪しからず。 | ||
| . | ||
| 6 | ふたまたをかざして笑うだいこ引き | そらまめ |
| <添削> ふたまたをかざして笑ふ大根引 | ||
| いい句です。少しエッチですが和やかな情景。 | ||
| . | ||
| 7 | 親子鹿夜明けの陽をうけ草紅葉 | 泉 |
| 「子鹿」「親鹿」は春の季語、「草紅葉」は秋の季語です。中八に | ||
| なっています。陽は鹿にも草紅葉のもかかります。考えてみてください。 | ||
| . | ||
| 8 | 女医さんの白衣キリリと冬の朝 | 初 霜 |
| いい句です。冷え込みが厳しいが今日も頑張ろう。生き生きとした女医さん | ||
| の姿が見えるようです。 | ||
| . | ||
| 9 | 透き通る一草庵の木守り柿 | さつき |
| いい句です。朝日に映える柿がおいしそう。 | ||
| 「木守り柿と」名詞の場合は送りがなは不要です。 | ||
| . | ||
| 10 | 櫨紅葉史料館に丸ポスト | 媛 香 |
| <添削> 秋澄むや文学館の丸ポスト | ||
| 「櫨紅葉」に「丸ポスト」では目が移ります。焦点をしぼりましょう。中六に | ||
| なるので「文学館」にしました。 | ||
| . | ||
| 11 | 若人の街にとまどう秋斜陽 | 峰 生 |
| 私は「秋斜陽」という言葉を知りません。句意がよく分かりません。悪し | ||
| からず。 | ||
| . | ||
| 12 | 紅葉道病後の妻と散歩する | 浩 風 |
| <添削> リハビリの妻に寄り添ふ紅葉道 | ||
| 「紅葉道」「散歩」は付き過ぎ。このように詠んでみました。早く元気になら | ||
| れるようお祈りします。 | ||
| . | ||
| 13 | しぐれ窓飲めば乗れずに日の暮るる | 峰 生 |
| 詩情がよく分かりません。考えてみてください。 | ||
| . | ||
| 14 | 枯れ深む山をつくづく見て独り | 彰 子 |
| 私の句です。裏山を見ては生き様を考える。 | ||
| . | ||
| 15 | 忘年会窓際族の目に光 | 千 柳 |
| 詩情がよく分かりません。考えてみてください。 | ||
| . | ||
| 16 | サイドミラーに秋の入日を連れ戻る | コスモス |
| <添削> 連れ戻るサイドミラーの秋入日 | ||
| 調子がよくないのでこのように詠んでみました。七七五が五七五になります。 | ||
| . | ||
| 17 | 蜂蜜はアンデスの香よ秋の朝 | 楓 花 |
| 私には句意が理解できません。悪しからず。 | ||
| . | ||
| 18 | 東福寺今年も紅葉見損じる | 菜の花 |
| <添削> 紅葉に万人集ふ東福寺 | ||
| 俳句は実体験での詩情を詠むものです。東福寺は京都五山の一つで | ||
| 紅葉の名所です。 | ||
| . | ||
| 19 | 病む足に衣(きぬ)を重ねて月仰ぐ | さつき |
| <添削> 病む足に衣重ねるや星月夜 | ||
| 「月仰ぐ」ですと説明になるのでこのようにしてみました。これで月を | ||
| 眺めている様子は分かります。お大事になさいませ。 | ||
| . | ||
| 20 | 明日雨と急ぎ移植の秋野菜 | 竹 豪 |
| いい句です。天候に左右される農作業は大変です。頑張ってください。 | ||
| . | ||
| 21 | つまみ捨(す)つ我が分身の木の葉髪 | 初 霜 |
| いい句です。年をとってくるとある時期抜け毛の多くなるときがあり、 | ||
| 侘びしさを感じます。大切な髪です、大事にしましょう。 | ||
| . | ||
| 22 | 木の葉雨芝居見物骨休め | そらまめ |
| 木の葉雨|芝居見物|骨休め|と三段切れになり、調子がよくありません。 | ||
| 「木の葉雨」とは木の葉が落ちる音を雨に見立てたもので、「木の葉雨」と | ||
| 「芝居見物」では意味不明のように思うのですが。考えてみてください。 | ||
| . | ||
| 23 | 山かげの五百羅漢や石蕗の花 | いなご |
| いい句です。山裾の目立たない所に寂しげに五百羅漢が並んでをり、 | ||
| 辺りには石蕗の花 がひっそりと咲いているという。季語がよく効いている。 | ||
| . | ||
| 24 | 大水車釣瓶落としの日を流す | コスモス |
| いい句です。情景を上手く詠まれています。 | ||
| . | ||
| 25 | 秋の暮れ永久保存したき空 | 楓 花 |
| いい句です。澄み切った秋空。できるもになら永久保存したいですね。 | ||
| . | ||
| 26 | 木枯らしや待ち人に倦む喫茶店 | 峰 生 |
| いい句です。待っているのは彼女でしょうか。待たせてはいけませんね。 | ||
| 季語もいいと思います。「木枯らし」は「木枯」と送りかなは不要です。 | ||
| . | ||
| 27 | ぶつ切りの大根煮ている妻の留守 | 彰 子 |
| 私の句です。今日妻はたまの外泊、久しぶりに台所に立つ。大まかな料理。 | ||
| 自分好みの味付けをする。 | ||
| . | ||
| 28 | 川の字に並びて写真七五三 | いなご |
| <添削> 子を中に石段上がる七五三 | ||
| 「川の字に寝る」と言いますが、「川の字に並ぶ」と言うのでしょうか。 | ||
| また、写真を撮ると言うのではおもしろくないのでこように詠んでみました。 | ||
| . | ||
| 29 | コスモスや記憶の中の母のこと | 初 霜 |
| いい句です。コスモスが咲く頃になると亡き母を想い出す。 | ||
| . | ||
| 30 | 車椅子孫に押されて菊花展 | 竹 豪 |
| <添削> 菊の香や嫁の寄り添ふ車椅子 | ||
| 孫は可愛いものと決まっているので俳句では使うのはよくないと | ||
| されています。このように詠んでみました。 | ||
| . | ||
| 31 | ふんわりとわた噴きており散歩道 | 浩 風 |
| <添削> ふんわりと棉新しき日和かな | ||
| 「わた噴き」は「棉吹く」のことでしょうか。散歩道は付き過ぎ。 | ||
| . | ||
| 32 | 回り道秋の入り日に時計見る | そらまめ |
| <添削> 回り道して時計見る秋の暮 | ||
| 俳句で「秋の入り日」とは言わないのではないでしょうか。このように | ||
| 詠んでみました。 | ||
| . | ||
| 33 | 大腸の検査の良くて紅葉晴れ | 浩 風 |
| <添削> 大腸の疑いはるる菊日和 | ||
| 調子がよくないのでこのように詠んでみましたが、いかがでしょうか。 | ||
| 「紅葉晴れ」は「紅葉晴」としましょう。 | ||
| . | ||
| 34 | 水遣りの手を止めて見る十三夜 | 楓 花 |
| <添削> 大声で妻招きゐる十三夜 | ||
| 「水遣り」とは「水撒き」のことではないでしょうか。「水撒き」は夏の季語です。 | ||
| したがって季重ねになります。また「月」と「見る」は付き過ぎです。 | ||
| . | ||
| 35 | 粧いも新たな秋に逢いに行く | 千 柳 |
| <添削> 粧いも新たな秋の開拓地 | ||
| 「逢いに行く」と思いは述べないほうがよいのです。 | ||
| . | ||
| 36 | 里山を彩る紅葉駆け上がり | 泉 |
| <添削> 古里の山もみいずる父祖の墓 | ||
| 原句ですと詩情に乏しく説明になります。また紅葉は山を下ってくるもの | ||
| ではないでしょうか。 | ||
| . | ||
| 37 | そぞろ寒朝の散歩の友まばら | 千 柳 |
| <添削> やや寒や淡き灯りの出湯町 | ||
| 説明的なのでこのように詠んでみました。 | ||
| . | ||
| 38 | 籾落とし夫婦仲良く秋の空 | 竹 豪 |
| <添削> 晴れわたけり夫婦仲良く籾磨 | ||
| 「籾落とし」は秋の季語です。調子がよくないのでこのように詠んで | ||
| みました。七七五になっています。夫婦で籾落としをする。会話も弾む | ||
| ことでしょう。うらやましい。 | ||
| . | ||
| 39 | 行く先のどの山見ても燃えるよう | 菜の花 |
| <添削> 行く先のどの山々も濃紅葉 | ||
| 季語がありません。「見ても」は省略しました。 | ||
| . | ||
| 40 | 枯菊のなかの一枝部屋に挿す | まこと |
| <添削> 枯菊の一枝挿しこむ鳥の声 | ||
| 説明的なのでこのように詠んでみました。 | ||
| . | ||
| 41 | 一天の青さに響く鵙高音 | 哲 朗 |
| いい句です。気分が壮快になる大きな句です。 | ||
| . | ||
| 42 | 直哉想へば晩秋の船の音 ??? (作家 志賀直哉) | 彰 子 |
| 私の句です。志賀直哉は尾道の千光寺山麓で「暗夜行路」を執筆しました。 | ||
| その志賀直哉を想っていると、ときどき汽笛が鳴ってくるのである。 | ||
| . | ||
| 43 | 冬耕のエンジン響く日曜日 | いなご |
| いい句です。家庭菜園か、日曜日のお休みに農作業に精をだしていい汗を | ||
| かく。気分爽快。 | ||
| . | ||
| 44 | 腰伸ばす仕草母似や稲の秋 | まこと |
| いい句です。年老いた母の仕草に似てきたという。親子ですね。 | ||
| . | ||
| 45 | ストッキングするりと履ける今朝の秋 | コスモス |
| <添削> ストッキングするりと履ける菊日和 | ||
| 「今朝の秋」は立秋の日の朝の爽やかな感じを言います。秋は「馬肥える」 | ||
| と言って食欲の増す季節です。したがって「今朝の秋」はどうかと思います。 | ||
| . | ||
| 46 | 冬時雨山の風車は動かざる | 石の花 |
| <添削> 一連の風車の止まる大枯野 | ||
| 詩情に乏しいと思います。「時雨」は冬の季語です。したがって「冬時雨」 | ||
| とは言いません。 | ||
| . | ||
| 47 | うたせ湯に肩を癒して夜の長き | 哲 朗 |
| <添削> うたせ湯に肩を癒しぬ夜長かな | ||
| 今日は疲れた、長々と肩に打たせ湯を浴びる。今夜はゆっくりと眠れそう。 | ||
| . | ||
| 48 | 遍路道何をおもふか夜の露 | 泉 |
| <添削> 遍路道何をおもふか夜の露 | ||
| 「遍路道」は春の季語。「夜の露」は秋の季語です。 | ||
| 句意がよく分かりません。悪しからず。 | ||
| . | ||
| 49 | 山静か木々はいよいよ冬に入る | 哲 朗 |
| <添削> ふるさとの山静々と冬に入る | ||
| 「山静か」「木々は」は言い過ぎになるのでこのようにしてみました。 | ||
| . | ||
| 50 | 二度咲きの金木犀が花いっぱい | 菜の花 |
| <添削> 一人立つ金木犀の二度咲きに | ||
| 「二度咲きの金木犀」ですから「花いっぱい」は省略したい。 | ||
| . | ||
| 51 | 溜池に初鴨飛来細波 | 媛 香 |
| <添削> 初鴨の水尾まっすぐにかがやけり | ||
| 「初鴨」は秋の季語、「鴨」は冬の季語。 | ||
| 「溜池」に「初鴨」「飛来」「細波」と言い過ぎです。省略しましょう。 | ||
| 「水尾」は「みお」と読み、水の流れる筋などうを言います。 | ||