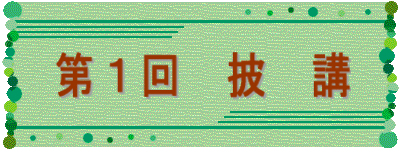
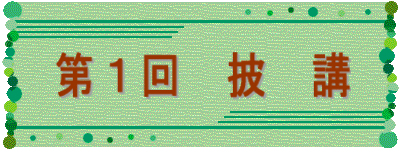
第一回若草句会の選句が終わりました。
私の添削と寸評をいたします。
みなさんの俳句がうまいのに感心しました。詩的センスがいいのですね。とかく自分ではできないと思い勝ちですが、自信をもってやってください。
添削と寸評についてですが、私にやれということなので力不足(役不足)ですが、務めさせてもらいます。これはあくまでも私が私なりに解釈し、私なりに添削し、寸評するもので、必ずしもこれがいいというわけではありません。こういう解釈、こういう作り方もあるんだなという程度に考えてください。
1 買い初めは一も二もなく季語の本
<添削> 買初に(かいぞめ)一も二にもなく季語の本
「買い初めは」は「買初めに」にします。一のも二にもなく季語の本を買ったという。俳句を始めようという意気込みが伝わってきます。頑張ってください。
2 孫を連れ凍てつく夜の帰り道
<添削> 孫連れて凍てつく夜の塾帰り
「帰り道」を「塾帰り」に変えてみました。具体的になるかと思いまして。孫の送り迎えはお婆さんの役割、孫と話しながら歩くのが楽しみでもある。
3 昭和二年生まれ辛夷に大きな芽
これは私の句です。私は戦中派です。喜寿を迎え、過ぎ去りし人生に思いをはせているのです。今年も辛夷に大きな芽がついています。よし、これからも大いに頑張っていこう。
4 紀伊の国梅ふっくらと咲き初む
<添削> ふっくらと梅の咲き初む紀伊の国>
上五と下五をいれかえました。この方が調子がいいように思って。
5 孫の笑み思い浮かべてみかんの荷
<添削> 孫一人思い浮かべてみかん食ぶ>
「孫の笑み」ですが、孫といえば可愛いものです。したがって、笑みまでいわなくていいと思います。「みかんの荷」は「みかん食ぶ」とより具体化させました。この方が臨場感がでるように思いまして。こたつに入って、蜜柑を食べながら遠くにいる孫を思い出しているのです。
6 初俳句思いつくまま雪光る
<添削> 雪の夜や思いつくまま初俳句>
上五と下五と入れ替えました。そして「雪光る」を「雪の夜や」に変えました。「雪光る」では雪を描写しており、雪が強くなります。作者は初俳句を作ったことに主眼をおいているのではないかと思いまして。
7 初詣で柏手響く静けさよ
<添削> 静けさを破る柏手初御空(はつみそら)
「初詣」と「柏手」そして「響く」は付きすぎです。添削句ですと晴れ渡った大空に柏手が鳴りわたっているのです。今年も思いを新たにして頑張ろうと思う。
8 木枯らしにカラスかしまし堀之内
<添削> 木枯らしにカラス舞ゐる城下町
「木枯らし」と「かしまし」はどちらもやかましいものです。どちらか除きましょう。そして「堀之内」は「城下町」に変えました。固有名詞を使うのは難しいものです。有名で美しい固有名詞は別ですが。
9 孫一人元日朝から初詣
<添削> 初孫の話上手や初詣>
「元日朝から」は中八です。中七にしましょう。添削句の方が臨場感がでます。初孫と一緒に初詣とは幸せですね。孫の話を聞いていると大変楽しい。初、初となるのもリズムとしていいのかも。
10 身の丈を聴きつつ渡すお年玉
<添削> 身の丈を柱に刻むお年玉
添削句の方が臨場感がでませんか。毎年お正月がくると、孫の身長を柱に刻みます。そして成長を喜ぶびます。孫はお年玉を貰うのが楽しみなのです。
11 嚔(くさめ)して旅のプランを練り直す
これは私の句です。嚔(くさめ)は「くしゃみ」のことです。私は旅行が大好きで年が明けると旅行のプランを練ります。あれこれ考えるのが楽しいのです。夜遅くまですることがありますが、いつの間にか冷えてきて風邪を引いたのです。
12 寒空を元気に遊ぶこども達
<添削> 寒空を揺るがす子供たちの声
子供達の元気な、そして大きな声が飛び交う。その声が寒空を揺るがすようであるという。元気いっぱい遊びまわっている子供達の様子がよく分かります。明るい俳句です。
13 新年や娘(こ)におぶさりて泪ぐむ
<添削> 新年や娘(こ)におぶさりて宮参り
「泪ぐむ」は感傷的が強いので除き「宮参り」にしました。子供の大きくなるのは早いものです。頼りになる娘におぶさって初詣でをしたのです。ほほえましい光景です。
14 成人式さわぎを起こす晴着かな
<添削> さわぎゐる成人式の晴着の娘
上五と中七を入れ替えてみました。この方がリズム感がよくなります。
15 初詣邪気を払うや鈴の音
<添削> 初詣ひときは高い鈴の音
「初詣」で切れ、「払うや」でも切れ、切れ切れになります。そこで添削句のようにしてみました。昨年は災害の多い年であった。今年は平和で幸せな年でありますようにと力一杯鈴を鳴らす。鈴の音はあたりの邪気を払うように鳴り渡るのである。
16 パソコンのスタート押すかな初仕事
<添削> パソコンのスタートを押すお元日
中八になっております。中七でのかな止めは感心しません。「かな」は最後にもってくるようにしましょう。 「初仕事」というと職業のようにとらえられるのではないかと思います。さあー、今年も一生懸命パソコンを勉強しよう。
17 新成人誓いも新た門出かな
<添削> 金髪の誓い新たな新成人
かな止めの場合いは上五から下五まで切れることなくつづきます。一句一章といいます。原句ですと 「新成人誓いも新た」で切れるのではないかと思うのですが。最近では金髪の新成人も珍しくなくなっています。
18 満月に突き刺さりをり天守閣
<添削> 満月の上りきってる天守閣>
「突き刺さり」は少々オーバーではないかと思います。「満月の上りきってる」と素直に表現してみました。満月に照らし出されたお城がくきりと浮かび上がって見えるのです。
19 冬の朝つどう体操顔赤く
<添削> 凍てる日のラジオ体操はじまりぬ>
うまく添削できません。悪しからず。体操をして「顔赤く」は当たり前かと思って削りました。素直に表現してみました。
20 駆け抜ける刻の速さよ年迎ふ
<駆け抜ける刻の速さよ鏡餅>
物がありません。俳句は物にたくして作ります。「年迎ふ」を「鏡餅」に変えてみました。「鏡餅」を見ながら一年をふりかえっているという句です。
21 沿線のどこまでつづく曼珠沙華
うまい句です。パソコンの手を休め外をみると横河原線の線路がまっすぐにのび、その沿線に真っ赤に咲いた曼珠沙華が咲いているのです。美しい風景で疲れが癒されます。
22 晴天のどさりと落ちる屋根の雪
<添削> 屋根の雪どさりと落ちる旅の宿
屋根の雪」を上にもってき、雪が晴天で落ちるというのはおもしろくないので「晴天」を除けました。「どさりと落ちる」はいいですね。
23 幸せの隣は不幸芋を煮る
これは私の句です。「幸せの隣は不幸」という言葉、「禍福はあざなえる縄のごとし」ということわざがありますが、しみじみと過去をふりかえっているのです。大好きなじゃが芋がぐつぐつとおいしそうに煮えています。
24 水仙の匂いに誘われ墓参り
<添削> 水仙の匂いただよふ生家にて
「匂いに誘われ」は中八になります。中八は指折り数えて避けましょう。
母は水仙が好きで沢山植えていました。久しぶりに実家に帰ってみるといっぱいの水仙が迎えてくれました。そのことを墓参して母に話しました。「墓参り」は秋の季語で、季重ねになります、「墓参り」を除けました。
25 古希過ぎて残り僅かな今日の朝
<添削> 古希過ぎて墨絵はじめる今朝の春
古希も過ぎたが、まだまだ意気さかん、今年から墨絵を始めようと思う。いつまでもお元気で。原句では物がないので何か物をもってきたいものです。「今日の朝」は季語ではありません。
26 紀三井寺の掃けど寄せれど枯葉降る
<添削> 落葉中三井寺の鐘ごんごんと
「紀三井寺の」は上六になるので「三井寺」としました。落ち葉が降りしきる中、ごんごんと鐘が鳴りわたる、という景です。夕暮れどきの哀愁を感じる句となっています。
27 手習いのパソコンで出す年賀状
ただいま、パソコンを夢中になって勉強中、なんとか年賀状が作れるようになった。お気に入りの年賀状ができ、満ち足りている。しかし、友達はどう評価してくれるだろうか。パソコンで作った年賀状をはじめて出す気持ちが分かるような気がします。
28 一団の白装束や初薬師
<添削> 一団のなまり言葉や初薬師
他郷から団体で初薬師にお参りしている。わいわいと賑やかにおしゃべりしているが、なまりがひどくて何を言っているのかよく分からない。「白装束」と「初薬師」は付きすぎるのでこのようにしてみました。
29 枯れかけたピンクの椿花つける
<添削> 枯れかけの色して椿落ちにけり
<添削> 椿咲ききってゐる昼下がり
椿といえばピンクを想像します。また椿といえば椿の花のことを言います。そこで「ピンク」と「花」を除けました。
30 骨折のピンちくちくとみぞれ降り
<添削> 霙降る骨折のピンちくちくと
上五と下五と入れ替えて見る方法もあります。考えてみてください。
大きな事故で大変でしたね。寒さが厳しいと痛さも激しくなることでしょう。ご同情申し上げます。ご自愛くださいませ。
31 外堀の噴水ぬるみ亀が鳴く
<添削> 水温みけり(みずぬるみ)亀がゐて鳥がゐて
「噴水ぬるみ」も「亀が鳴く」も春の季語です。
水温む頃になりますと、亀も鳥もうきうきしてきます。
32 初詣で奉納吟の厳かに
<添削> 初春のあたり震わす奉納吟
「初詣」・「奉納吟」・「厳かに」は言い過ぎ、付きすぎていると思います。何もかも言っています。俳句は簡潔に表現したいものです。考えてみてください。
33 霧薄れほのかに浮かぶ開閉橋
<添削> 露寒やほのかに浮かぶ開閉橋
「霧薄れほのかに浮かぶ」は説明になります。季語を変えて「霧薄れ」を「露寒や」にしてみました。今日は冷え込んで霧が多く発生する。その霧がだんだん薄れてきて赤い開閉橋が浮かび上がって見えてくるという、幻想的な美しい光景であります。長浜の開閉橋のことでしょうか。いい写真が撮れましたか。
34 朝夕に孫と二人で落ち葉はく
<添削> 朝夕に孫と二人で落葉はく
素直な句ですね。平和なほほえましい光景です。落ち葉を掃きながら孫と会話を交わすのが楽しいのです。孫に教え、孫から教わります。きっといいお孫さんになられることでしょう。名詞はかなを除き「落葉」とします。
35 冬空に満天の星キラキラと
<添削> 頬凍つる満天の星キラキラと
「冬空」・「満天」・「星」はみな天体のことです。俳句は十七音(字)の短詞形の文芸ですから、省略し、簡潔に表現するのがいいのです。添削句ですと、パソコンを打ち終え外へ出てみると寒い、今日は冷え込むなーと両手に息を吹きかけながら空を見上げると、満天の星が降るようにきらめいている。しばらく見とれてたたずむ。きっと明日はいい天気になることでしょう。
36 初詣宮社響く柏手や
<添削> 柏手の社(やしろ)に響くお元日
初詣・宮社・柏手とみな共通した言葉が並びます。あれもこれも言い過ぎ。省略しましょう。
添削句でも十分初詣の感じはでていると思いますが。
37 餅つきの昔懐かし道の駅
<添削> 餅搗きにかけ声の飛ぶ道の駅
俳句では「餅つきの昔懐かし」といったような感懐を直裁に表現しない方がいいのです。
添削句のようにしてみました。旅行中道の駅に立ち寄ったら、たまたま餅搗きがおこなわれていました。とりまいている大勢の人が杵を下ろすのに合わせてかけ声をかけているのです。
38 初夢はもみじの手のなか古希も過ぎ
<添削> 古希過ぎにけり初夢は鬼ごっこ
原句の意味が良く分からないので、このような句にしてみました。古希を過ぎた初夢は、子供のころよく遊んだ鬼ごっこだったのです。夢の中でしばし童心にかえったのです。中七が中八になっています。
39 妻植えしやっと花咲く寒椿
<添削> 病みがちな妻の植えたる寒椿
うまく添削できないですみません。「寒椿」といえば花の咲いた姿を想像するわけです。したがって「花咲く」を除きました。病みがちな妻の方が思いいれが強くなるかと思ってこうしました。ご免なさい。病みがちな妻が丹精を込めて育てた寒椿が立派に咲いたというのです。さぞ嬉しかったことと思います。
40 元旦や雪に洗はるここちして
うまいですね。元旦の日の心情をうまく表現されています。雪に洗われるとは、さぞ清々しい気持ちになったことでしょう。
41 初場所や夜空にひびく跳ね太鼓
<添削> 寒中の下町を行く触れ太鼓
大相撲の太鼓を「跳ね太鼓」というのか知りません。「触れ太鼓」というと、呼び出しが太鼓を打ちながら町にふれて歩くことです。寒中になると大相撲の触れ太鼓が両国界わいに鳴りひびきます。夜空に太鼓というのもどうかと思いまして、このようにしてみました。
これで添削と寸評をおわります。初めてのことでどこまでしていいのか戸惑いました。言い過ぎたこと、間違ったことがあったことと思いますがお許しください。冒頭に述べたように役不足な私が勝手に解釈した結果ですので悪しからず。少し難しかった点は追々分かってきます。
では今から2月分の句造りを始め次回も必ず投句して下さい。それでは
2月の句会でお会いしましょう。